皆さんが医療機関で受診すると、窓口で医療費の1割~3割の一部負担金(自己負担)を支払います。
この一部負担金が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分を後日申請していただくことで、高額療養費として払い戻されます。
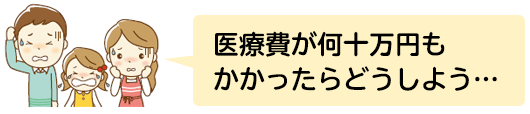
高額療養費があるから安心です!
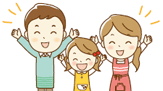 高額な医療費がかかる場合でも、皆さんの自己負担には上限があります。所得に応じて、月ごと(月の1日から末日まで)の自己負担限度額が定められています。
高額な医療費がかかる場合でも、皆さんの自己負担には上限があります。所得に応じて、月ごと(月の1日から末日まで)の自己負担限度額が定められています。
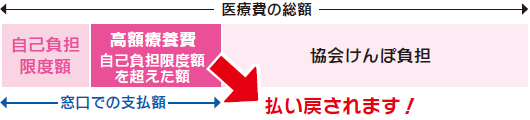
自己負担限度額は所得や年齢によって変わります!
●70歳未満の方の自己負担限度額
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額(月ごと) | 多数回該当 |
|---|---|---|
| 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)× 1% | 140,100円 |
| 53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)× 1% | 93,000円 |
| 28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)× 1% | 44,400円 |
| 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 低所得者※1 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 低所得者……区市町村民税非課税者である被保険者および被扶養者、または、低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者および被扶養者の場合
●70歳以上の方の自己負担限度額(平成29年8月~平成30年7月)
平成29年8月診療分から、70歳以上の方の自己負担限度額が引き上げられました。
平成29年7月以前の自己負担限度額については、『社会保険新報』平成29年7月号に掲載しています。| 標準報酬月額 | 自己負担限度額(月ごと) | 多数回該当 | |
|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
| 28万円以上 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)× 1% | 44,400円 |
| 26万円以下 | 14,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
| 低所得者Ⅱ※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ※3 | 15,000円 |
||
※2 低所得者Ⅱ……区市町村民税非課税者である被保険者の場合
※3 低所得者Ⅰ……区市町村民税非課税者である被保険者および被扶養者で、年金収入が年間80万円以下等の場合
70歳未満の方の自己負担限度額の計算ルール
月の1日から末日までを1か月として計算します。
2 受診者ごとに計算
 同じ世帯でも1人ずつ計算します。
同じ世帯でも1人ずつ計算します。
3 病院・診療所ごとに計算
複数の病院・診療所にかかっている場合は、別々に計算します。
4 歯科は別に計算
同じ病院に歯科があって同時にかかっている場合は、別々に計算します。
5 入院と外来は別に計算
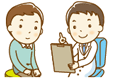 同じ病院に入院と外来でかかっている場合は、別々に計算します。
同じ病院に入院と外来でかかっている場合は、別々に計算します。
保険薬局での自己負担額は、処方せんを発行した病院・診療所で支払った自己負担額と合算して計算します。
6 21,000円以上が対象
上記1~5に当てはまる自己負担額21,000円以上が計算対象です。
7 保険適用外の医療費は対象外
入院時の食費負担や差額ベッド代などは対象外です。
 |
多数回該当 直近12か月の間に同一世帯(保険証の記号・番号が同じ)で3回(3か月)以上高額療養費に該当した場合は、4回目から自己負担限度額が減額されます。 世帯合算 同一月に同一世帯(保険証の記号・番号が同じ)で21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合は、自己負担額を合算して計算します。 特定疾病 血友病、人工透析、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の患者は、「特定疾病療養受療証」を提出すると、自己負担限度額が1か月1万円(標準報酬月額53万円以上で人工透析の患者は2万円)になります。 |
「高額介護合算療養費」の制度もあります。
事前に限度額適用認定証を用意しておくと、
窓口での支払いが限度額までで済みます!
保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提出すれば、病院・診療所の窓口での支払いが、所得に応じた自己負担限度額までで済みます。
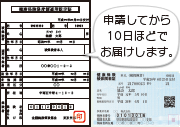 入院・外来いずれの場合でも、高額な医療費がかかりそうなときは、協会けんぽに事前に申請して、交付を受けておくと便利です。
入院・外来いずれの場合でも、高額な医療費がかかりそうなときは、協会けんぽに事前に申請して、交付を受けておくと便利です。
70歳以上の方は「高齢受給者証」で所得を確認できますが、前年度の所得が非課税の方は申請が必要です。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで



