編集委員 小池 敏夫
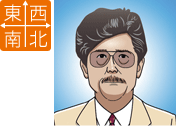
5月の声を聞く頃、海外旅行の添乗員をしている娘がスペインから帰国。早々にネットで何やらやっている。何気に「また何処かに遊びに行く気だろう?」と尋ねると、「当然じゃん。人の旅や遊びの世話だけじゃ、とてもやってられないよ。たまには自分の旅をエンジョイするんだ」ときたもんだ。
件の娘様、ほぼ1週間おきに、お客様を引き連れてヨーロッパへご旅行。結構じゃございませんか。オヤジなんて生まれてこのかた、地図とテレビ番組でしか、ヨーロッパなんてお目にかかったことがございません。はたから見れば贅沢の極み。本人にとっては単なるお仕事。見すぎ、行きすぎは不感症の根源。何となくわかるような気もします。さて、前置きはほどほどにして本題に入りましょう。
娘いわく、「屋久島に行くよ。苔むす森を見に行くんだ。それと縄文杉。山中泊でまわってくる」とやけに簡単にのたまう。確かに、わが家には娘一人しか子宝がございません。女の子だからといって、人を頼って生きるのでは人生辛かろうと、要らぬ親心でたくましく育てたつもり。おかげさまでたくましくなりすぎた。
「山歩きした経験もないのに、大丈夫なの? 装備もないし」と問うと、「ガイドを頼むから大丈夫」とくる。「山中泊で縦走するには、シェラフやテント、食料などを含めて、少なくとも20kg程度の荷物を担がなきゃならないんだよ。それに、平地との標高差も最高で1,900m以上あって、かなり急峻な山岳路の山行になるから無理だよ」と言うと、「ダイジョ〜ブ。ガイドが持ってくれるから」だって。勘弁してよ。自分の荷物は自分で担ぐの。なんと脳天気な娘さんだこと。「ガイドはシェルパじゃないよ。アンタ、添乗員をやっててお客さんの荷物を持ってあげる? ありえないでしょ。ましてや、屋久島は年間総雨量が平地で4,000mm以上、山間部では10,000mmにも達するといわれていて、毎日のように雨が降る。そんなところで、山の経験もない者が、野営しながら歩けると思ってるの。トイレだってまともにないし、屋久島は世界自然遺産に指定されているから、ゴミや排泄物の垂れ流しはご法度。自分のものは自分で担いで下山するというのがルール。アンタにゃ、山中泊の縦走は10年早い」と、これが良識ある山男のつとめとばかりに言ってやりました。
「ところで、行くのはいいけれど、現地での移動の足はどうするの?」と問うと、「路線バスは本数が少なくて不便だし、タクシーを使うとかなり出費がかさむから、レンタカーかな」「だって、あなたは車の免許はもっているけれど、免許取得後に一度も車を運転したことがないじゃない」「大丈夫だよ。島の道なんて一本道で、まっすぐ走っていれば出発点まで戻って来られる程度の道だから」だって。なんという恐ろしい言葉。ここまで世の中をなめているとは。こんな人間に育てたつもりはない。このまま放って置くわけにはまいりません。そこで、「しょうがないな。それじゃオヤジがガイド兼ドライバーをやるしかないか。そうすれば送迎もしてくれないガイドに大枚払う必要はないし、移動も自由になるでしょ」ということで、仕方なさを装いつつ、お財布代わりの俄かガイドとして、屋久島攻略作戦に参戦決定。娘のお供で屋久島に行っちゃいました。娘がカミサンにいわく、「オヤジ、なんだかんだと言いながら、私よりも行く気満々だよ!」。
ウキウキ準備を始めて気づきます。やけに財布が軽くなるな〜。そりゃ〜そうでしょう。数十年前の道具がいまさら使えるわけもなく、すべて最初から調達し直し。「昔取った杵柄が役に立つのは気持ちだけ」。この頃になると後悔が…。「後悔先に立たず」とは、よく言ったものです。
さて、屋久島は、九州本土最南端の佐多岬から約60kmの黒潮の流れの中に浮かぶ周囲約130km、直径約30kmの円形の島。島の中央には標高1,936mの宮之浦岳をはじめとして、1,000mを超える急峻な山々が40座以上も連なる山岳島。海岸地帯での年間平均気温は約20℃。ところが、山頂帯での気温は8℃。亜熱帯から寒冷地の気候までが一つの島の中に存在し、植生の変化は著しい。人口は13,290人余り。レンタカーの数たるや、島内に1,000台(本当かね?)。
ここでお約束の縄文杉詣で。屋久島に行ったら、縄文杉を見ずして何をか語らんや。標高600m付近の荒川登山口より、岩壁と、眺望を隠すようにブラインドのごとく林立する杉で覆われたトロッコ道と、本格的な山岳路を登ること5時間(約10km)。やっと縄文杉に巡り合う。早朝4時に宿舎を出発。縄文杉にたどり着いたときは昼も間近。昼食もそこそこに、もと来た道を下る。縄文杉での滞在時間は数秒から数分。混雑時は立ち止まらずに一方通行の通路を流れる。それでも宿舎にたどり着く頃にはどっぷり日も暮れて…。
縄文杉を間近で見ての感想は…と問われれば、登山道全体が大小取り混ぜて杉だらけ。縄文杉にたどり着く頃には、「ああ、これが縄文杉ね」、そして宿に帰り着いて一言、「もういいわ」。感想はあっても、感動が見当たりません。「杉(過ぎ)たるは及ばざるが如し」とは、まさにこのことを言うんですね。さすがに昔の賢者は的を得ているなんて、変なところで感動。
ちなみに、屋久島に生息する杉のすべてが屋久杉かと思いきや、樹齢1,000年以上のものを「屋久杉」と称し、100年から1,000年未満のものを「小杉」、100年未満のものを「地杉」と呼ぶらしい。固有名詞らしき名称のついた杉は樹齢2,000年を超えるもので、たとえば「縄文杉」は6,900年から7,200年との説もある。実際は4,000年程度ともいわれているが、それとてとてつもない樹齢を重ねているわけで、本当は感動しなきゃいけないのかも。その他に、「大王杉」「弥生杉」が3,000年、「紀元杉」「翁杉」が2,000年。そもそも杉の平均的な寿命は500年程度といわれているので、屋久杉の偉大さは格別。これまた杉の話にハマりすぎると、誰ぞやに「過ぎ(杉)たるは及ばざるが如し」と言われかねないので、このあたりで…。
さてさて長くなってまいりました。いよいよ纏めに入りたいと存じます。先に紹介したとおり、屋久島は、熱帯魚が遊ぶサンゴ礁やウミガメが産卵する砂浜を有し、まさに亜熱帯の海に浮かぶ島ですが、山頂には雪と氷の冬が訪れる島でもあります。山々に降る多量の雨と海辺に輝く太陽が、表情豊かな屋久島の自然を作り上げています(何となく観光ガイド的な言い回しになりました)。
ところで、海岸沿いには、ガジュマルという木が生息しています。「屋久島はガジュマルの生息域の北限にあたり、熱帯産のイチジクの仲間で、幹から多数の気根をたれ、それが土着し、やがてはどれが元の幹か区別できないようになる」と、志戸子海岸ガジュマル園の案内板に書いてある。園内を一巡すると、樹高約15mの巨大ガジュマルをはじめとして、さまざまなサイズのガジュマルが鬱蒼と葉を茂らせている。空中を横に伸びた幹からは、気根が簾のように無数に垂れ下がっており、薄暗いガジュマル林に一層怪しげな雰囲気を醸し出している。かたや、標高500m以上の高地に生息する巨大杉と、標高数mに生息する巨大ガジュマルが一つの島に共生していることに不思議を覚える。
そのガジュマルであるが、わが家にも数十年前、観葉植物として鉢植えながら生息していた時期がある。樹高1.5m、何の手入れもせず伸びるにまかせ、枝葉はボサボサ状態。見かねた義父が、盆栽心でありがたくも剪定を施す。バッサバッサと小枝を切り落とし、本人は悦に入っている。さて、義父が帰った後のこと、ガジュマルは…と見ると、剪定された枝先から白い樹液がタ〜ラタラ。それはイチジクの実をもいだときのよう。それからひと月、看病の甲斐もなく、わが家のガジュマルは生涯を終えたのでした。人間でいえば、出血多量による失血死といったところ。すべからく、やりすぎは禁物。まさに「過ぎたる葉、およ葉ざるが如し」。な〜んちゃってね。
屋久島から引き上げてきて2週間足らずの5月29日。突如、口永 良部島が噴火。ウミガメの産卵を見に行った永田浜から目の前に見え た島です。島民の方々は屋久島の宮之浦という町に避難されており、 最近ではニュースにもなりませんが、いまだ避難生活を続けておられ ます。屋久島から距離にして12km。手の届きそうな距離にありなが ら帰島できない島民の皆様の心労を思うとき、過ぎるくらいの支援を 送りたいと思う今日この頃です。



