年金は、年金を受ける資格を得ると同時に、自動的に支給されるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行う際の添付書類や留意点などについて説明します。
請求書の事前送付(男性61歳、女性60歳)
年金の支給開始年齢に到達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対して、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録を印字した年金請求書(事前送付用)と年金の請求手続きのご案内をご本人宛に送付します。
請求書の提出
年金請求書の受付は、支給開始年齢に到達してからになります。戸籍や住民票などは、年金の受給権発生日以降に交付され、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。支給開始年齢に到達する前に年金請求書を提出された場合は、受付できません。 特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ制度はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。
【請求時に必要な書類等】
●年金請求書 お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備えています。
●すべての方に必要な書類
| 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか【個人番号の記載がないもの】 | 生年月日を明らかにできるもの。 ※単身の方で、年金請求書に住民票コードを記入された場合には、戸籍抄本などの添付は省略できます。 |
|---|---|
| 受取先の金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード等(コピー可)。 年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。 |
| 印鑑 | 認印可 |
留意事項
平成27年10月5日より、希望者には住民票に個人番号の記載が可能となっておりますが、日本年金機構では、現在、個人番号の利用や受け取りができません。年金請求書等に添付する住民票(記載事項証明書を含みます)については、個人番号の記載がないもので提出をお願いします。なお、住民票コードの記載があるものは、引き続き提出できます。
●本人の厚生年金の加入期間が20年以上で、配偶者または18歳未満の子がいる方に必要な書類
| 戸籍謄本(記載事項証明書) | 請求者との続柄および配偶者や子の氏名・生年月日の確認。 |
|---|---|
| 世帯全員の住民票 ※ | 請求者との生計維持関係や住民票コードの確認。 |
| 配偶者の収入が確認できる書類 | 生計維持関係の確認。【所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等】 |
| 子の収入が確認できる書類 | 生計維持関係の確認。義務教育終了前は不要。高等学校在学中の場合は、在学証明書または学生証等の添付が必要。 |
※ できるだけ住民票コードの記載があるもの・個人番号の記載がないもので提出をお願いします。
留意事項
本人の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生(共済)年金の加入期間が20年以上の方は、年金請求者の収入を確認きる書類が必要となります。
●本人の状況により必要な書類
| 年金手帳 | 基礎年金番号以外の年金手帳を持っている場合。 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険に加入したことがある場合(7年以内であれば再交付可能)。添付できない場合は理由書が必要。 |
| 年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入していた期間がある場合。 |
| 年金証書 | 他の公的年金から年金を受けている場合(配偶者を含みます)。 |
| 医師または歯科医師の診断書 | 1級または2級の障害の状態にある子がいる場合。 |
| 合算対象期間が確認できる書類 | 海外在住の期間がある場合は、それを証明する書類等。 ※詳細は、日本年金機構ホームページ等でご確認ください。 |
年金の決定と受け取り
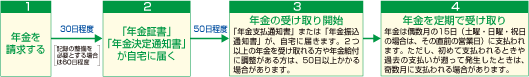
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
全国の相談・手続き窓口
(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで



