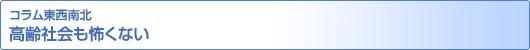編集委員 関野 豊
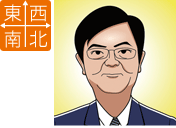
最近、健康寿命という言葉 を耳にします。少し前まで、 寿命といえば平均寿命を指 し、2014年度の日本の女性 の平均寿命は86.83歳で世界 1位、男性も80.50歳で世界 3位に位置しています。
ところが、平均寿命には、他の人の支援・介助を必要とする期間も含まれます。これに対して、健康寿命は、健康上の問題で日常生活が制限されない期間をいい、2013年では、女性が74.21歳、男性が71.19歳となり、この健康寿命を長くしようという政策が着手されています。しかしながら、健康とは自分自身で維持するものではないでしょうか。私が目標とする「ピンピンコロリ」だと、寿命=健康寿命となるのですが…。
私の住んでいる地域は、分譲住宅とマンションで合計1,000戸を超え、分譲住宅地となって30年以上経過しているT市の中でも2番目に住民の平均年齢が高く、70歳を超えています。私も居住して30年以上ですが、会社人間だったため、地域との関係が希薄でした。しかし、先日、定年を意識して、公園デビューにならい、地域デビューで地区の懇親ゴルフに参加しました。参加してビックリ。64歳の私が最年少、最高齢は87歳で、同じ組の方の話では「70歳を超えてようやく小僧扱いされなくなった」とのこと。サラリーマン川柳にもありましたが、まさに「70歳、オラの村では青年部」の状況です。
高齢者が多いことから、地域の有志で、地域防災の啓蒙活動が行われています。「防災のイロハ」の講座が年2回開かれ、すでに14回も開催されています。阪神淡路大震災の当時に神戸市灘区の生協に勤務されていた方を講師に招き、あの大震災をどのように生き延びたのか、地域住民として何をすべきか、何が準備できるのか等の講義を受け、皆で討議します。また、この講座の一環として、使われていなかった井戸を復元し、防災井戸として借りています。
平均年齢70歳を超える自治会での共助(地域住民が助け合って災害に対応する)と言えば、2014年11月に長野県北安曇郡白馬村でマグニチュード6.7、住宅全壊31棟・半壊56棟という大きな地震(長野県神城断層地震)がありましたが、地域の方々がお互いに救出し合い、死者0人だったというケースがあります。それこそが目標です。わが自治会でも、防災訓練を定期的に年1回開催して、自治会の倉庫に備え付けてあるカケヤ、ハンマー、バール、のこぎり、電動チェーン等を実際に作動して確認したり、実演での訓練などを行っています。訓練に参加してまたビックリ。参加者の元気なこと。カケヤを貯水池のマンホールに叩きつけ、さびついているマンホールのふたを開けたのには感心しました。防災器具を使用した地区防災員(これも70歳以上の地域住民の方です)の実演もあり、大変充実しています。
皆さん、なぜこんなに元気なのか。昨年11月下旬に、地域の「仲間つくりの会」懇親会に参加して、その理由の一端がわかりました。囲碁等の趣味のサークル、ウオーキング等の健康維持のためのサークルなど、7つのサークルがあり、延べ150人の方がいろいろな活動に参加しています。元気だから地域活動を行っているのか、地域活動を行っているから元気なのかはわかりませんが、元気で前向きなのは間違いありません。懇親会の席上でも、それぞれ自分が所属するサークルへの勧誘が行われていました。健康に留意しつつ、周囲と積極的に交わりをもつことが、結果として健康寿命を延ばしていることを実感しました。目指すは、日野原重明さんや瀬戸内寂聴さんですね。