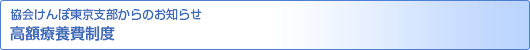被保険者(加入者ご本人)および被扶養者(加入者ご家族)ごとに、同一保険医療機関(外来・入院・歯科外来・歯科入院別)と保険薬局等で同一月内に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費を請求すると、自己負担限度額を超えた額の払い戻しが受けられます。
高額療養費ってなに?
高額な医療費がかかった場合、自己負担限度額を超えた額をご加入者に払い戻す制度です。
Point
●払い戻しの計算は、1 か月単位で行います。
●同一保険医療機関にかかった場合でも、外来・入院・歯科外来・歯科入院は別の計算となります。
●差額ベッド代などの保険外の負担額や食事の自己負担額は、払い戻しの対象となりません。
どの部分が払い戻しになるの?
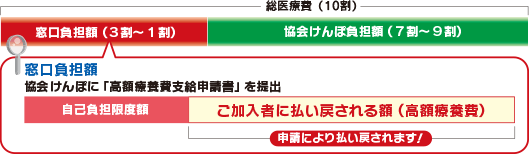
自己負担限度額は所得区分と年齢によって変わります
| 被保険者の 所得区分 |
世帯単位*1 [同一月内(外来+入院)] |
|
|---|---|---|
| 70 歳 未 満 |
区分 ア (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
区分 イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
区分 ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
| 区分 エ (標準報酬月額 26万円以下) |
57,600円 |
|
| 区分 オ (被保険者が住民税 非課税者等) |
35,400円 |
| 被保険者の 所得区分 |
個人単位 (外来のみ) |
世帯単位*1 [同一月内(外来+入院)] |
|
|---|---|---|---|
| 70 歳 以 上 75 歳 未 満 |
❶現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で 、「高齢受給者証」の負担割合が3割) |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
❷一般所得者 |
12,000円 |
44,400円 |
|
❸低所得者Ⅱ*3 |
8,000円 |
24,600円 |
|
| ❹低所得者Ⅰ*4 | 15,000円 |
- *1 世帯単位………個々の窓口負担額が21,000円以上となった場合に、合算の対象となります。
- *2 多数回該当……直近1年間で高額療養費に3回以上該当した方が、4回目以降の自己負担分の払い戻しを請求する場合( 「限度額適用認定証」を利用した月も回数に含まれます。)
- *3 低所得者Ⅱ……被保険者が住民税非課税者の場合
- *4 低所得者Ⅰ……被保険者および被扶養者が住民税非課税者で、年金収入が年間80万円以下等の場合
計算例
所得区分:区分 ウ(標準報酬月額28万~50万円)の健保太郎さんが入院。
保険適用となる総医療費100万円のところ、保険証を提示して30万円を保険医療機関等の窓口で支払った場合。
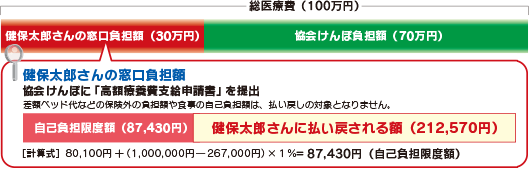
申請前にチェック!! 高額療養費の留意点
●同一世帯で同一月内に窓口負担額が21,000円以上となった加入者が2人以上いる場合などは、窓口負担額を合算して、その合算した額が自己負担限度額を超えたときも払い戻されます。70歳以上の方は、窓口負担額が21,000円未満でも合算されます。
●払い戻しは、レセプト(診療報酬明細書)の確認後となるため、診療月から3か月以上かかります。
便利な「限度額適用認定証」をご利用ください
「限度額適用認定証」を利用すると、1か月ごと(1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額まで注1となり、高額療養費(払い戻し)の申請が不要注2となります。
- 注1 保険医療機関(外来・入院・歯科外来・歯科入院別)と保険薬局等では、それぞれでの取り扱いとなります。差額ベッド代などの保険外の負担額や食事の自己負担額は、対象外となります。
- 注2 同一月内に入院や外来など複数受診がある場合、高額療養費の申請が必要となることがあります。
実際にどれくらいの窓口負担になるの?
総医療費(10割):100万円 窓口負担割合:3割
所得区分:区分 ウ(標準報酬月額28万~ 50万円)の場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「限度額適用認定証」を…
| 提示しない 場合 |
300,000円(3割負担)を保険医療機関等の窓口で支払い、高額療養費の申請をすることで、212,570円が払い戻されます。払い戻しまで、3か月程度かかります。 |
|---|
▼
| 提示した 場合 |
87,430円(自己負担限度額)を保険医療機関等の窓口で支払い、高額療養費の申請が不要となります。 |
|---|
申請前にチェック!! 「限度額適用認定証」の留意点
申請の流れは、『社会保険新報』平成27年10月号をご覧ください。
●「限度額適用認定証」の有効期間は、「限度額適用認定申請書」を受け付けた日の属する月の1日(健康保険の資格を取得した月の場合は、資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。
●「限度額適用認定申請書」受付月より前の月の「限度額適用認定証」は、交付できません。日程に余裕をもって申請してください。
●70歳以上の方は、「高齢受給者証」を窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
「限度額適用認定証」の発行には、1週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで